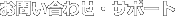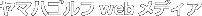誰もが、彼のことを「誠実な人」と言う。
プレッシャーの下でも、頂点を極めた歓喜の下でも、彼が礼儀正しさを失うことはない。ただ控えめに周囲の人たちへの感謝を口にし、後は、練習場で一人黙々と球を打つ。年齢を重ねるごとに強さを増し、2012 年には43 歳で初めての賞金王に輝いたプロゴルファー藤田寛之。
彼の誠実さは、何よりもゴルフという競技へ向けられたものである。「ゴルフはごまかしが利かない。逃げた瞬間に、もう二度と僕の方を見てくれなくなるからね」。そう言って笑った後で、ゴルファーは一つの秘密を教えてくれた。冷静な表情とは裏腹に、彼の胸の内にはいつも、高みを目指し続ける挑戦者の熱い想いが在ることを。
野球と釣りに彩られたごく普通の小学校時代。ゴルフは、そんな僕の当たり前の生活の中に、ある日、何の前触れもなく滑り込んできた。学校のグラウンドで、ゴルフクラブで遊んでいた友人と行き合ったのが、僕とゴルフの最初の接点である。その日から、僕は時々、父親の6番アイアンを持ち出して、校庭でボールを打っては拾いに行くという遊びを延々と繰り返すようになった。ゴルフというスポーツについては何も知らなかったけれど、ボールが芯を食った時の感触や、空に向かって描かれる真っすぐな軌道が面白くてしょうがなかった。楽しくて、楽しくて、人がいない場所を探すのも、飛んでいったボールを長い時間かけて回収するのも、ちっとも苦ではなかった。
当時の僕にとって、ゴルフは決して“当たり前の環境”ではなかったのである。ジュニアのころからレッスンを受けてきた選手と違い、僕の前にはゴルフ場はおろか、練習場の扉すら開かれてはいなかった。だが、「ゴルフがしたい」という想いに突き動かされて自分なりの練習を積み重ねてきた先には、確かに、プロゴルファーとしての生活が待っていたのである。
今、こうして自分の来た道を振り返ってみると、そこに、たった一つの真実があることに気付く。それは、高みを目指す熱い想いを抱き、その気持ちから逃げないですべきことをやり続ければ、誰もがいつか、自分のありたい姿に辿たどり着けるということである。終わりのない階段を上り続けることでしか見えない風景―それは、ゴルフが僕に教えてくれた一番大切なものである。
第1回. 「ひとカゴ」のルール16.05.09 UP
志とか夢とか目標とか、人によって呼び方は違うかもしれないが、「自分はこうありたい」という熱い想いが、全ての原点であることは間違いない。僕にとって最初の志は、やはり、大学3年生の時にはっきりと自覚した「プロゴルファーになりたい」という想いだろう。当時、専修大学ゴルフ部に所属していた僕は、初めて真剣に自分の将来を考え、「やはり自分にはゴルフしかない」と思い至り、1992年2月に葛城ゴルフ倶楽部の研修生となった。
研修生時代は、僕の人生の中でも最も死に物狂いで練習した時期である。プロになるという明確な目標に向かって完全燃焼した濃密な時間だったが、当時のことで今も鮮やかに蘇ってくるのは、夢に向かって走り続けた充実感よりも、日々、「自分は何のために頑張っているのか」と自問し続けた内省的な自分の一側面である。

当時、僕は既にゴルフがごまかしの利かないスポーツであること、さぼった瞬間にそっぽを向かれるような冷徹な精神性を有する競技であることを知っていた。しかし、人間の弱さとでもいおうか、僕は時々、「今日は練習をやめて帰りたい」と思うことがあった。物事がうまくいかない時や、どうしようもなく疲れている時。このまま帰ってテレビでも見たいと思うことはあったが、そんな時は一呼吸して、「ひとカゴ(100球)だけ打って帰ろう」と自分に言い聞かせた。ショットがだめなら、アプローチでもパターでもいい。とにかく100球打って練習を切り上げるように決めていた。
厳密に言えば、これも一種のごまかしかもしれないが、僕はそうやって自分の逃げたい気持ちと折り合ってきたのである。プロになるという志と、そこから逃げようとする自分とをつなぎ止める細い糸、それが「ひとカゴ」のルールだったのかもしれない。調子がいい時には体が悲鳴を上げるまで練習に打ち込むことができたが、どうしてもやりたくない時は「ひとカゴ」のルールを徹底してゴルフと向き合い続けた。1992年10月、僕はプロテストに一発合格する。僕の最初の志は、自分の努力がきちんと報われる形で実ったのである。










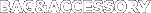
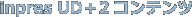
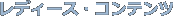





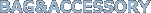
 inpres special
inpres special
 inpres special for LADIES
inpres special for LADIES
 GOLF LOVER
GOLF LOVER
 inpres owners club
inpres owners club
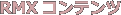




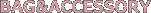
 WORLD of RMX
WORLD of RMX
 MY BEST RMX for DRIVER
MY BEST RMX for DRIVER
 MY BEST RMX IN THE BAG
MY BEST RMX IN THE BAG

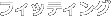

 YPAS(ワイパス)
YPAS(ワイパス)
 YPAS開催スケジュール
YPAS開催スケジュール
 ヤマハゴルフスタジオ高輪
ヤマハゴルフスタジオ高輪